会社が掲げる目標は、現場の実情を本当に分かっているのだろうか。
無理な数値を達成しろと言われる一方で、現場の責任者(トップ)は結果を求められる。
だからこそ、達成するために数字をコントロールするしかなくなる。
その結果、本来は便利であるはずのシステムが不正な数字に合わせて使われ、
かえって現場を縛り、仕事をやりづらくしてしまう。
さらに問題なのは、数字を操作した人が「できる人」として評価され、
誠実に働く人ほど報われないという現実だ。
優秀な人がやる気を失い、チームはギクシャクし、
目標を達成してもお客様には迷惑がかかっているそんな矛盾が起きている。
そもそも、その数値を決めている人は現場を理解しているのだろうか。
そして、会社が本当にフォーカスすべきところは“そこ”なのだろうか。
現場の声を無視した数字目標がもたらす歪み
現場を知らない人が作る”机上の目標”
現場の状況を知らないまま設定された目標ほど、現場を苦しめるものはありません。
人員不足や時間帯成果の状況を無視した平均化した理想の数値だけが独り歩きし、その達成を当然のように求められる。
上司からの指示は「とにかく目標数値を達成しろ」。
でも、現場で働く私たちには、それをどう実現するのかという具体的なサポートはほとんどありません。
せめて、人員さえいればなんとなるかもしれません。
しかし、人件費にも目標値があり、やたらめったらには増員できません。
結局、頑張れば頑張るほど無理が生じ、数字だけが評価の基準として残る。
「そこじゃないのに」という思いを抱えながら、今日も現場は走らされています。
達成のために数字をコントロールせざるを得ない現場
システムが”便利”から”矛盾の象徴”に変わる
達成できなければ責められる。
その恐怖が、現場を数字のコントロールへと追い込みます。
正直な数値を報告すれば未達成とみなされ、上司から指摘される。
だから仕方なく、報告上の数字を調整して“見た目の達成”を作り出す。
その結果、本来は便利であるはずのシステムが、操作された数字を前提に動くために、現場では使いづらくなる。
現場が現場を苦しめるような、矛盾した構造ができあがっているのです。
数字を正しく扱うことができず、正しい分析が成せれない。
改善しなければならない課題が見つからず、やらなければならないタスクも見つからない。
やがて“正確さより整合性”が優先される職場になってしまう。
正直者がバカを見る!そんな職場が生まれる理由
不正が評価される”逆転構造”
数字を上手く合わせた人が評価され、正直に報告した人が叱責される。
そんな場面が増えています。
正確な報告よりも「結果を出したこと」が重視されるため、誠実に働く人ほど損をする。
やる気のある人や真面目な人ほど、その理不尽さに気づき、次第に心が離れていきます。
チームの中では「どうせ頑張っても変わらない」という空気が広がり、信頼関係が崩れていく。
正直者が報われない職場は、長くはもちません。
優秀な人が去り、残るのは
数字だけが得意な人たち。
そんな歪んだ評価構造が、現場の疲弊を深めています。
目標設定の本当の目的を見直すとき
数字の先にある”人の動き”を見よう
数字を追うことが悪いわけではありません。
問題は、その数字が誰のために 何のためにあるのか、が見えなくなっていることです。
本来、目標とは現場の力を引き出すための指標であるはず。
でも今は、現場の声が届かず、数字だけが独り歩きしている。
会社が本当に見るべきは、結果ではなく、そこに至るプロセスやお客様の満足。
現場の努力を数字だけで測らず、上層と現場が同じ方向を向く仕組みをつくることが大切です。
目標は“達成のためのノルマ”ではなく、“良い仕事を支える道しるべ”であるべきだと感じます。
まとめ
数字を追う前に”何のための目標か”を問い直す
目標を達成しても、現場が壊れてしまっては意味がありません。
数字を合わせることが目的になった瞬間、職場の本質は見失われてしまう。
大切なのは、数字の裏側にある「人の努力」と「現場の現実」を見つめ直すこと。
無理な目標が生む悪循環を断ち切るには、まず「そこじゃない」と声を上げることから。
それが、現場と会社の信頼を取り戻す第一歩になるのだと思います。
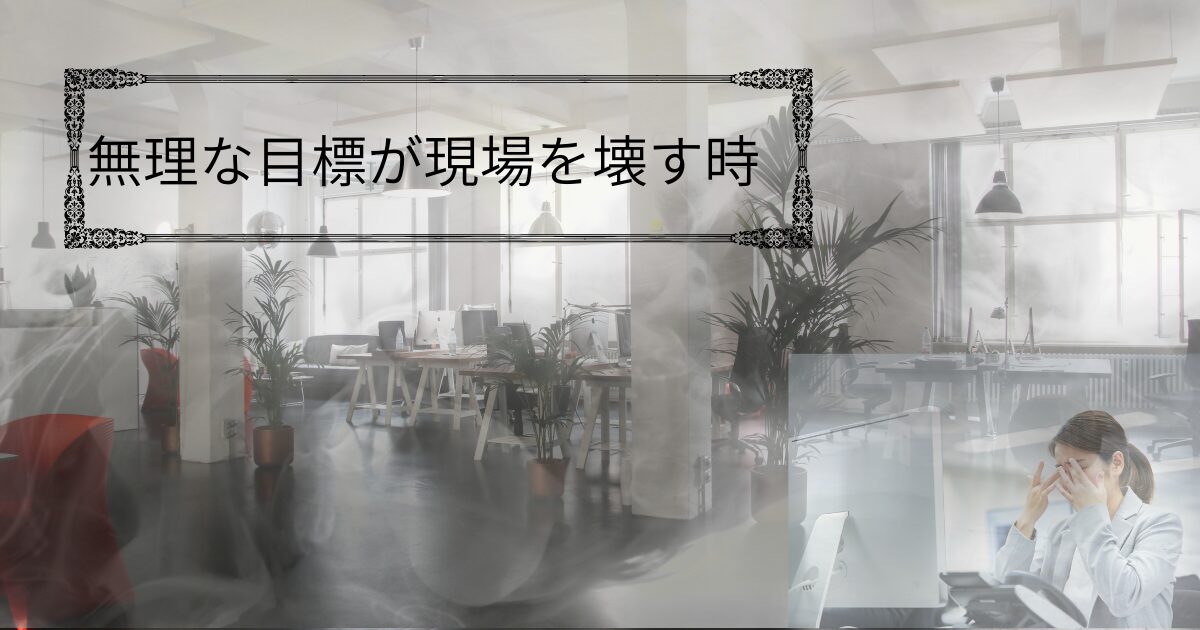
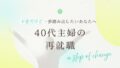

コメント