転職活動をするとき、あなたは何を一番重視しますか?
仕事内容?
報酬や給料?
会社の規模?
人それぞれ、ここは譲れないというポイントがある時はずです。
では…あなたは、何歳まで働きますか?
60歳?70歳?80歳?
以前は定年60歳(ちなみに私の父は60歳で会社をリタイアして亡くなる83歳まで一度も働きに出ることはありませんでした。)
しかし、今は60歳で辞めても、年金だけで生活できる人はそう多くありません。
日本では2021年4月から「高年齢者就業確保措置」という制度が始り、国も70歳まで働くことを促しています。
つまり、「70歳まで働ける環境を作ってね」と企業にお願いしてる段階で制度も少しずつ広がっています。
だからこそ、今から70歳まで続けられる仕事に就くのか、70歳を見据えて再度転職するのか選択が必要な時代になっています。
この記事では実際に60〜80代が働く現場のリアルや40代から意識したい仕事選びのポイントを体験談も交えてご紹介します。
楽しく、無理なく、長く働けること。
そして70歳になっても社会とのつながりを持ちながら暮らせること。
そんなヒントを一緒に見つけていきましょう!
こだわるべきポイント
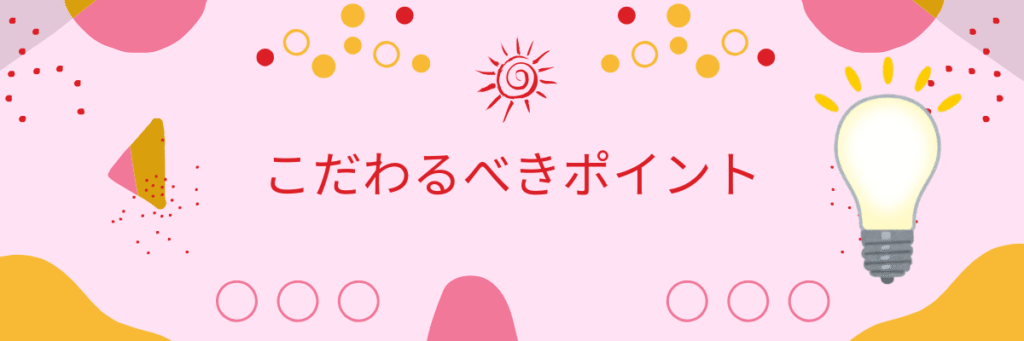
- 目的・優先条件を明確化
40代前半で転職するのと50代後半で転職するのでは目的が違います。何の為に転職するのかを明確にし、譲れない条件をしっかり考えることが重要です。 - キャリアの棚卸しと強みの分析
今までの経験とスキルを把握し、自分がその企業・仕事内容に合った即戦力をアピールすることが大切です。
要は企業に、自分を雇ったらどんな得があるかをアピールするのです。 - 柔軟な働き方・雇用形態の選択
60代以降も働くのであれば長く働く事ができる職場であるかを重視しパート・契約・業務委託なども視野に入れるのが現実的です。60代以降は賃金が減るケースが多めです。自分が納得できる条件か、生活に問題がないかも確認しましょう。
60代以降の仕事
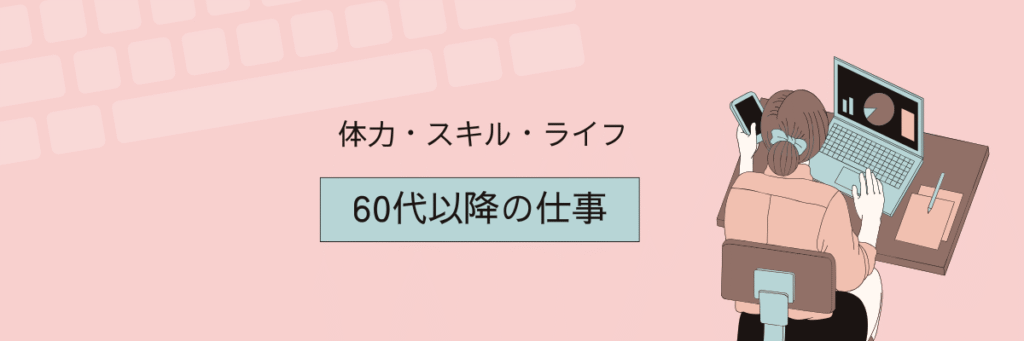
60代以降は、体力や健康・家族の状況などに合わせて無理なく働ける仕事・職場選びつつ、ハローワークやシニア求人サイトの積極的な活用がポイントです。
- 自分の体力・ライフスタイル・やりがいを重視する。
- 履歴書・職務経歴書はできる限り更新し、人生経験や社会人スキルもアピールする。
- 収入面以外に「社会とのつながり」「生きがい」「柔軟な働き方」も「意識して選ぶと長続きしやすい
転職に有利な年齢は何歳まで?
従来言われていた「35歳転職限界説」は実質的に過去のものとなり、年齢で転職を諦める必要はありません。
とはいえ2024年転職成功者の平均年齢は32.7歳。最も転職比率が高いのは25〜29歳で29歳で36.7%、次いで30〜34歳で23.1%となっています。
しかし、企業は即戦力・マネジメント経験を持つミドル層への採用ニーズを高めており、年齢上限が昔ほど厳しくなくなっている状況です。
「何歳までが有利」と固定せず、世代ごとに強みや戦略を持って転職すれば、幅広い年齢でチャンスがあります。
- 若いほどポテンシャル採用されやすいですが、年齢が高くなるほど「専門性」「経験値」が問われる
- ITなど人手不足分野では、年齢よりもスキルや意欲が重視される傾向が顕著です。
- 65歳までの雇用確保が企業に義務付けられるなど制度的にも長く働く基盤が整っています。
2025年現在は40代以降もチャンスあり
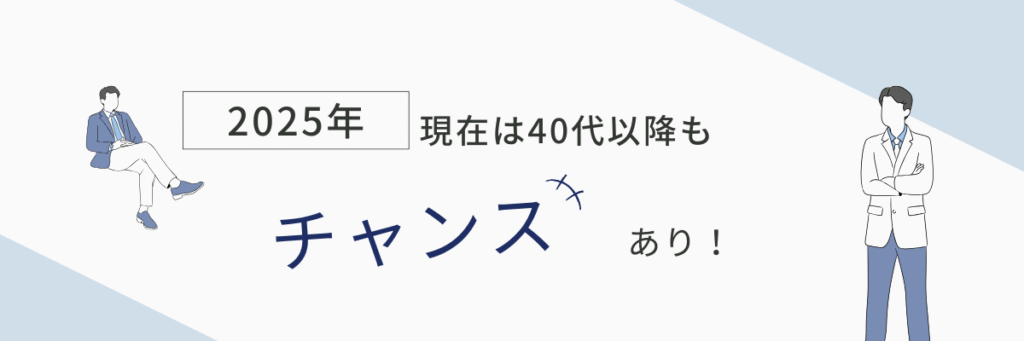
2025年は「ミドルシニア元年」とも言われ戦略的なキャリアチェンジが可能な環境が整っています。
近年、40代〜60代の転職希望が大きく増加。特に50代前後では団塊ジュニア世代が育児・教育などの出費や役職定年・再雇用による収入不安を抱え、転職の意欲が高まっています。
企業側も即戦力を求める傾向が強まり、経験豊富なミドルシニア層の採用ニーズが急上昇。
若手人材の採用難、事業の多様化や高度化による「知見のある人材」の必要性が背景です。
例えばある転職サービスでは2019年比で40代〜60代の新規登録者数が約140%増加。
50代で転職した人の約4割が年収アップを実現しているというデータもあります。
87歳の女性が制服を着た日
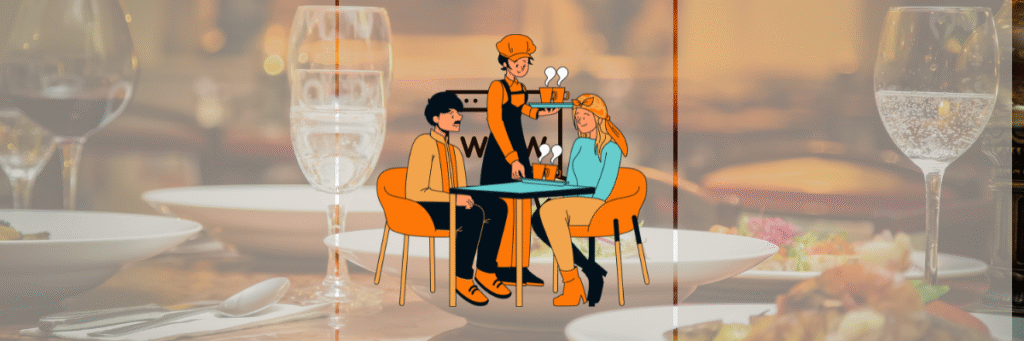
〜高齢者が働く現場から見えるもの〜
87歳、制服を着てフロアへ
「いらっしゃいませ」
ある日、87歳の女性が大手ファストフード店の制服に袖を通しました。
鏡に映った自分の姿に、少し照れくさそうに笑っていたかもしれません。
彼女に任されたのは、フロアのお仕事。
お客様に商品を運んだり、ゴミ箱を片付けたり。
厨房の慌ただしさから少し離れた場所で、でも確かに必要とされる役割でした。
店舗は3階まで客席があり、移動はすべて階段。
ゆっくりと階段をのぼる姿
そのお店は3階まで客席があり、エレベーターはありません。
若いスタッフでも息が切れるほどの上り下りを、彼女は一段一段踏みしめていました。
特に3階のゴミ箱はすぐにいっぱいになりがち。
そんなとき、彼女が黙々と片づけてくれると「いてくれるだけで助かる」とスタッフたちは口を揃えます。
夏の暑さと、体の限界
夏が近づき、体力の壁が
ゴールデンウィーク前に始まった仕事。
「動けるうちはやってみたい」そう笑顔で話していた彼女でしたが、夏の暑さが体に堪えました。
体調不良で早退したり、休む日が増えたり。
接客では少し砕けた言葉遣いがお客様に驚かれることも。
それでも、フロアを任される安心感は大きく、現場には確かな存在意義がありました。
「とても楽しかった」
数か月後、彼女はお店を辞めました。
それでも、後日「やってみてどうだった?」と聞かれたとき、返ってきたのは意外なほど明るい答え。
「とても楽しかった」
短い期間でも「働けたこと」自体が、彼女にとって誇りであり、生きがいにつながっていたのでしょう。
働くことの意味
このエピソードは、一人の挑戦を超えて、社会全体の課題を映し出しています。
• 人手不足を補う力
外食産業をはじめ多くの現場で、高齢者は欠かせない存在になりつつあります。
• 本人にとっての意味
「社会とつながる」「役に立てる」ことは、健康や心の張り合いにもつながる大きな要素です。
• 続ける難しさ
ただし、体力や環境の壁は避けられません。階段の上り下りや暑さへの対応など、働き続けるには工夫が必要です。
日本の「70歳就業社会」とのギャップ
政府は「70歳まで働ける社会」を推進しています。
実際、総務省の調査によると65歳以上の就業率は25%を超え、年々上昇しています。
しかし「働ける人」と「働きたい人」がいても、働き続けられる環境が整っていなければ長続きはしません。
87歳の女性が体力の限界で辞めざるを得なかったように、現場のリアルにはまだ大きな壁があります。
あなたは何歳まで働きたいですか?
87歳の女性が残した「楽しかった」という言葉は、ただの感想ではなく、働く意味そのものを示しているように思えます。
「人の役に立てること」
「社会とつながっていられること」
それが、働くことの根っこにある喜びなのではないでしょうか。
もしあなたが60代〜80代になったとき
どんな働き方をしていたいですか?
そして「働くこと」に、どんな意味を見いだしていたいですか?
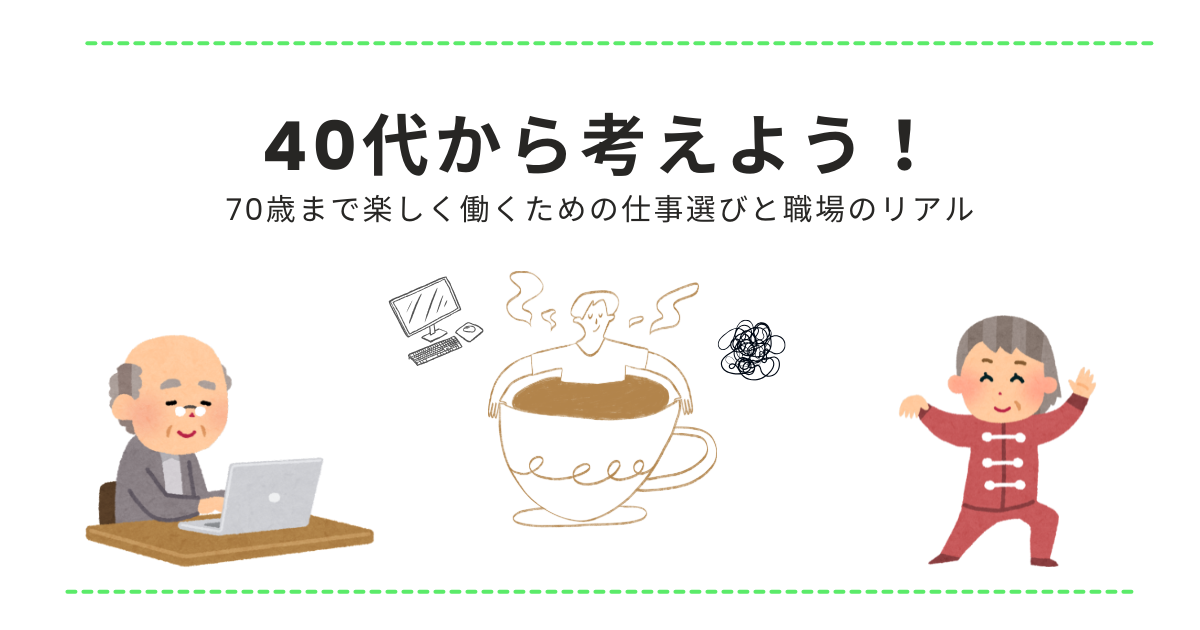
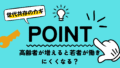

コメント